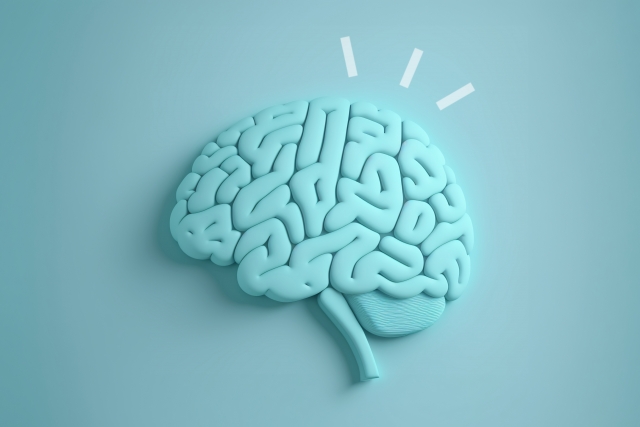
認知症との戦い方の正攻法は、認知機能が低下していることにできるだけ早く気づき、進行を止める、または遅らせるための生活を始めることです。
MCIの前なら脳の健康をいつまでも維持することができるし、たとえMCIだったとしても、認知症を発症せずに逃げ切ることができます。
ただし、残念ながら日本の7割の人が、認知症予防のため特に何もやっていません。
MCIの対応策として推奨されているのが、次の3つです。
生活習慣、運動を中心とした脳の活性化、食生活です。
この内、運動と食生活は予防に関心があれば、個人でもできますが、生活習慣としてのコミュニケーションはある面、地域力が必要になります。
猛烈社員として人生を送ってきた高齢者が、定年になって地域に出た時、どれだけの地域が受け入れる体制になっているのでしょうか。
介護保険制度が平成27年度に改正され、四日市でも平成29年4月から「介護予防。日常生活支援総合事業」が導入されました。
これは、もう専門職だけでは高齢者を支えられない公助(税による公の負担)、共助(社会保険制度)とともに互助(住民相互の支え合い)の力を活用しながら、地域全体で高齢者を支える仕組みです。
住み慣れた地域で、非専門職による支援(住民、民間企業等さまざまな資源)も活用しながら地域全体で高齢者を支える仕組みです。
これすなわち、「地域包括ケアシステム」の構築です。
これが施行されてから、5年が経過しますが、この住民主体の取り組み地域は訪問型も通所型も半分の地域しか実施されていません。
またその後の経緯においてもこの助け合いの制度の導入未実施の地域において増える状況でもありません。
是非、多くの市民がこの制度を知り、お互い助け合う体制の実施に向けて取り組むことが必要になります。
そのため、自治会、社会福祉協議会、老人会等の組織が地域にいろいろあると思いますが、各組織の取り組みが早急に望まれま
す。
















-11-500x607.png)







